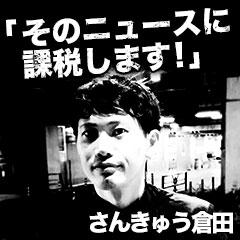毎週木曜日配信 さんきゅう倉田「そのニュースに課税します!」
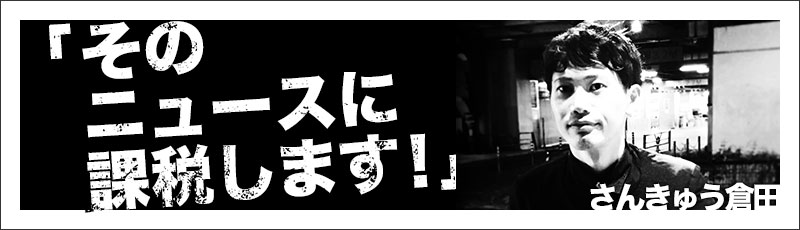
不動産や住宅と深い関係がある税金。
よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属、元国税局職員のさんきゅう倉田さんが、税金に係わるニュースについて解説します。
今回は、江戸時代の脱税に関する解説です。(リビンマガジンBiz編集部)

(画像=写真AC)
元 国税局職員 さんきゅう倉田です。
僕が宇宙から地球を見て言う最初の一言は「申告書は青かった」です。
江戸時代の税
江戸時代の税金といえば、田畑を対象とした年貢が中心でした。税率は、40~60%といわれており、幕府・大名領によって税率が異なりました。幕府領は税率が低く、大名領は税率が高かったそうです。
このように、農民には年貢がありましたが、商人や現在でいうところの個人事業者や法人にはどのような税がかけられていたのでしょうか。
この当時は、免許税や営業税のような一定の金額を納める制度はあったようですが、所得に対しての課税はされていなかったそうです。稼げば稼ぐほど儲かる商人たちに比べ、農民は年貢として多くを徴収されていました。そんな農民たちが脱税に手を染めるのは、至極当然のことだったのしょう。
脱税の方法
少しさかのぼりますが、太閤検地が行われる前は、課税標準となる土地の大きさは農村の自己申告制でした。現在の日本の申告納税制度に近かったといえます。だから、みんな嘘の申告をして土地を狭く装うだけで脱税ができました。なんて単純な脱税方法なんでしょう。
太閤検地では、多くの田畑が実際に計測されたので、この方法で脱税することができなくなりました。しかし、年貢にも税率があるので、現在の税務調査のようなものが必要です。この調査は、現代のように事業を開始して4年経つとやってくるようなこともなく、滅多に行われなかったようです。200年間調査がなかったという運が良い地域もあったそうです。あったとしても、調査や徴収のやり方はずさんで、農民がゴネれば、調査官を担当する武士も強く出られず、納税を少なくすることは容易だったそうです。現代の納税者とやってることはあまり変わらないように思います。
さらに、検地後に新たに果樹栽培などを始めた場合は、税金がかかりませんでした。もちろん、自主的に申告すれば課税の対象となったのでしょうが、そんな意識の高い納税者はいませんでした。今でいう、「無申告」です。

(画像=写真AC)
幕府領は、調査を担当する武士が圧倒的に少なく、検地がままならなかったため、徴収もゆるかったようです。豊作の年でも「天気が悪かったので全然収穫できなくて…」などと言えば、税率を下げてもらえました。台湾かき氷の口当たりのように優しい武士。農民たちの間では、年貢率を下げてもらうための虚偽の説明を考えるのが流行ったそうです。きっと遅刻の言い訳のように、「親が倒れて」とか「目覚ましが鳴らなくて」とか「電車が遅れてて」とか言ったのでしょう。
また、古来より伝わる脱税として、役人を接待して、課税標準を有利に判定してもらう方法もありました。
時代によって課税の方法は異なりますので、脱税や節税の方法も変化があります。
室町時代は家の間口の大きさに対して税が課されていました。市民たちは課税を逃れるために、玄関を小さくして、奥に長い家を建てるようになりました。
飛鳥時代には、歴史の授業で習う「租庸調」以外にも、21〜60歳の男性には60日の公共事業の労働にかり出されるという税がありました。この時代には、「戸籍をごまかす」脱税が流行りました。20歳なのに70歳で登録したり、性別を偽ったり、自分が死んだことにして、税を逃れていたそうです。
税金によって人の暮らしが変わるのは今も昔も変わりません。
ちなみに芸人として売れると、高額な年収をもらい、その分だけ累進課税で多くの税金を支払います。それに加えて、週刊誌などに追われて有名税を支払うことになります。
ちなみに私は、今の有名税を支払ったことがありません…。
早く課税対象になりたーい!