【新連載】なぜ不動産会社はトップ営業マンに依存してしまうのか
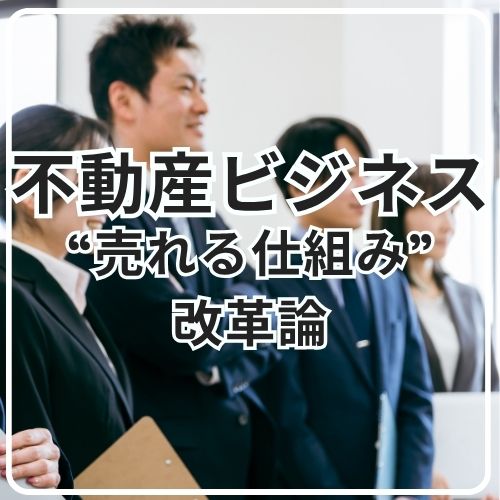 不動産ビジネス“売れる仕組み”改革論
不動産ビジネス“売れる仕組み”改革論

画像=PIXTA
不動産業界は少子高齢化や人口減少、トップ営業マン依存、デジタル化の遅れなど、多くの課題に直面しています。
本連載では、リクルートでの豊富な経験とモデスティでの伴走コンサルティング実績を持つモデスティ・長野卓将氏が、「売れる仕組み」をいかに構築し、不動産会社を持続的に成長させるかを解説。経営戦略、人材育成、営業力強化、マネジメントの仕組み化まで、明日から実践できるヒントをお届けします。
依存は“楽”だが、組織を弱くする
人口減少が進む現在、不動産会社の課題の一つが「トップ営業マン依存」です。かつては少数精鋭が数字を牽引し、会社は伸びました。しかし採用環境が変わった今、特定の人に寄りかかる体制は、組織全体のモチベーション低下や離職リスクを招きます。短期的には合理的に見える選択でも、長期では脆さを残す。そこで本稿では、依存が生まれる三つの理由を整理し、明日から実践できるノウハウを紹介します。
理由1:トップ営業マンに任せるとすぐに成果が出て、社長自身の手間が省けるから
創業期の社長は自ら売るしかありません(私も実際そうでしたし、今も営業マンです笑)。営業マンを雇う余裕がない中で、自社の商品を自分の営業力で広げる。その延長で、営業畑出身の経営者ほど「売れる人が会社を引っ張るのが自然だ」という成功体験を持ちます。私自身も、リクルート入社当初は順風満帆ではなく、二年目に「通用しないから辞めろ」と厳しい助言を受け、そこから血のにじむような努力を重ねて結果を出しました。
管理職時代には、トップ営業マン数名を率いて高い実績も出しました。こうした体験は、意思決定を最短距離で進めやすく、手間も省ける――結果として「トップに任せておけば業績が上がる」という思考を強化します。加えて、トップは“自然に育つものだ”という思い込みも生まれがちです。若い頃の苦労は、年を重ねると忘れやすい(こういうと社長を老害みたいに言っているように聞こえますが、私も還暦を迎えて簡単に成功したんだと思って調子にのっていたら、最近、恩師に怒られました・・・)。成功の心地よさが、依存を後押しするのです。さらに、トップ営業マン数名で数字を作ると、合意形成も早く、自分のやりたいことを直線的に進められる手触りが残ります。これもまた、手間を惜しまずに組織を育てる発想を遠ざけます。
極論、トップに任せておけば社長の手間が省け、他の業務に集中できるように見えます。ところが、その“省力化”は教育投資の先送りでもあります。短期の便利さと引き換えに、育成の遅れと属人化のリスクが静かに積み上がっていく――ここを直視できるかが分岐点です。
理由2:人を育てるための設計図やフローを持っていない
多くの社長は高度な営業スキルを持っています。しかし「自分でできる」と「人にできるようにさせる」は別物です。
研修の現場でも、「教えたいが言語化できない」との声を多く聞きます。たとえるなら、水泳が得意でも、水が怖い子どもに恐怖を取り除き、息継ぎやクロールの“型”を順に教えるのは難しいのと同じです。教育は設計と手順が要る仕事です。ところが、設計がないままに任せると、偶然の成功だけが残り、再現性が生まれません。その難しさに直面すると、「営業マンは勝手に育つものだ…」とうそぶきたくなる。けれども、それでは社長の技量が組織に展開されず、結局トップ頼みが続きます。育成の覚悟と言語化が欠けていること――これが二つ目の要因です。
教育に必要なのは、
- 営業マンの課題の把握
- 教育プログラムの設計
- 言語化した教育プログラムをわかりやすく解説
- 営業マンが実践
- できなかった点を営業マンと一緒に反省
- 修正して反復する
です。たとえ一流のプレーヤーでも、説明の順を誤れば伝わりません。相手がつまずく地点を想定し、言葉をそろえ、できるまで伴走する。地味な作業ですが、この手間を引き受けた会社ほど、再現性のある戦力が増えていきます。
理由3:離職が怖く、過度に“ちやほや”してしまう
かつてビジネスの現場では、谷底からはい上がる“ヤングライオン”のような人材が次々に台頭しました。ところが今は状況が違います。採用市場は厳しく、おとなしい人材も増えています。
そのため「今いるトップ営業だけは絶対に辞めさせられない」という発想が強まり、待遇や裁量が過度に偏る。機嫌を損ねて退社されるくらいなら、と遠慮が重なる。結果、他の営業のモチベーションが下がり、職場の空気も悪化します。トップ営業以外の人材は「どうせ中心にはなれない」と感じ、挑戦が減る。数字は一時的に保てても、育成が止まれば、やがて成長は頭打ちになる。離職が怖いがゆえの“依存の固定化”こそ、第三の要因です。
処方箋:ナンバー2を計画的に育て、依存を“仕組み”に変える
解決策はシンプルです。トップではないがトップになれるポテンシャルを持つ人材を、順番に育てること。育成が回り始めれば、
- トップ本人も地位に安住せず努力を続ける
- 仮にトップが辞めても会社は容易には傾かない
- 「自分も将来は会社を背負う存在になりたい」という前向きな動機が組織に広がる
という良い循環が生まれます。依存の状態を、再現性のある「売れる仕組み」へと置き換える第一歩は、“ナンバー2の教育”です。特別な仕掛けを増やす前に、候補者を明確にし、順番に育てる。その一点から始めましょう。育つ人が二人、三人と増えれば、数字は個人戦からチーム戦へと移り、会社は依存から自立へと変わっていきます。
最後にもう一度。解くべきは“個の力に寄りかかる構造”です。ナンバー2の育成から始め、依存を仕組みに変える。今日決めて、明日一人目を指名する――それだけで、会社の未来は動き出します。
ナンバー2の教育方法については、次回ご紹介いたします。
|
著者プロフィール リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)に入社後、マンション・戸建分譲会社・仲介会社・注文会社・リフォーム会社等を担当し、各地でマネージャーを歴任。「虎の穴研修」(新人育成研修)やトップ営業研修を開発。鹿児島支社長を経て独立し、2012年に株式会社モデスティを設立。 |

